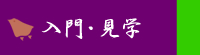|
小唄の完成・・・
さて、江戸時代の末期に産声をあげた小唄ですが、本格的に花開くのは明治に入ってからとなります。激動の幕末から明治維新は、芸能の世界にとって厳しい時代となります。江戸っ子の足は芝居小屋から遠のき、花柳界のお弟子もめっきり減って清元お葉も苦しい生活を強いられ、小唄の新作どころではありませんでした。
しかし世の中が次第に落ち着き、お葉は新政府の高官たちの座敷へ出入りするようになります。さらにお葉を引き立てたのが、あの「横浜の富貴楼お倉」でした。
維新の騒動で火が消えたようになっていた江戸の花町は政府高官とそれをとりまく政商たちによって、旧に倍する繁栄を極めます。三菱の岩崎弥太郎は横浜の富貴楼を舞台に政府高官と歓談し、新橋南地(烏森)は西郷を取り巻く軍人たちの根拠地となり、「煉瓦地」(新橋)は伊藤博文、井上馨ら文官の根城となったといいます。
明治13年頃より、東京の代表的な花街、新橋と柳橋は「新柳二橋」といわれ、新政府びいきの新橋には政府高官たちが通い、柳橋には江戸芸妓の本場として通人、粋客が集まったようです。これら花街では、最初の頃こそ「騒ぎ唄」と呼ばれる賑やかな流行歌が歌われましたが、やがて江戸情緒のある粋な曲が好まれるようになっていきます。
明治初期の花街の繁栄ぶりを江戸時代にたとえて、町人の豪商が金にあかして『大尽遊び』をしていた『元禄時代』、 それに比べて明治中期の花街は同じく金に糸目をつけない遊び方でも風流を競い「通」とか「粋」が好まれる『享保時代』といわれることがあります。 それに比べて明治中期の花街は同じく金に糸目をつけない遊び方でも風流を競い「通」とか「粋」が好まれる『享保時代』といわれることがあります。
そんな明治中期の花街では、粋でいなせな江戸小唄のスポンサーとしての旦那衆が続々と現れました。この旦那衆の中に、自分で酔余に作った小唄の歌詞に作曲をさせ、それを聞いて喜ぶ粋人が出てきます。こうして江戸小唄は新曲がどんどん作られるようになり、最初はその場限りの座興だったものが、有名な曲だけが口伝で伝えられるようになり、やがて記録され後世に残されるようになったのです。
次(小唄の「は」)へ
|