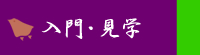|
小唄の流派
現在の小唄には、いくつかの流派があります。
ほとんどは、大正時代以降に正式な流派として成立したものです。
明治も終わりの頃、政界、財界には、まだ粋な方たちが大勢いて、お座敷に小唄はなくてはならないものでした。その中に「小唄をただ通人の余技にしておくのはつまらない。一流を立てたらどうか」と進めた方がいました。そこで"堀小多満"さんが家元になって「堀派」を始めたのが大正6年のこと、これが小唄の流派の第一号になりました。
芝愛宕町に稽古場を開いた「堀派」に続き、赤坂氷川町では"田村てる"さんが「田村派」を、木挽町(現在の東銀座)で"吉村ゆう"さんが「吉村派」を、"蓼胡蝶"さんが新橋で「蓼派」を立て、"小唄幸兵衛"さんは「小唄派」の名乗りを上げ、男性としては初めての家元となりました。さらに昭和に入ると「永井派」「佐藤派」「浅井派」「田毎派」「岩井派」「松葉派」と続々と新しい流派が誕生しました。
私たちがお稽古をしている「春日流小唄」というのは、"春日とよ"さんが家元として昭和3年に看板をあげた流派「春日派」の小唄です。
浅草の鶴助
家元の"春日とよ"さんは、明治14年に浅草は花川戸の生まれで、母は大工の棟梁の娘という生粋の江戸っ子ですが、父が英国人という当時としては珍しい生い立ちでした。その波乱万丈の生涯を一言でご紹介するのはとても難しいのですが・・・浅草で芸者をする母に育てられ、幼い頃から祖母や母から歌沢、踊り、常磐津の手ほどきをうけ、清元、長唄、一中節、荻江、義太夫とありとあらゆる芸事を習い自らも十六歳のとき「鶴助」という名で芸者に出ました。
大正の初期、東京の花街は24ヶ所あり、芸妓の数でいうと新橋1200名、浅草734名、神楽坂600名というように大変栄えていました。その中でも、江戸小唄を特意とする芸妓として「浅草の鶴助」と名があがるほどの名手だったようです。
小唄 春日流
その後、自らが営んでいた待合の屋号「春日」を取って「春日とよ」として一流
を立て、小唄の師匠に専念することになります。小唄を世に広めるため、放送やレコードの録音、弟子の指導はもちろん、作曲にも非凡な才能を発揮します。
特に後半生に力を注いだ作曲活動は、とても進歩的な考えによるものでした。
「小唄本来の江戸前さと粋さを保ってゆこうとしても、時代も変わり昔とは違っています。今の人に江戸前になれ、粋になれといっても出来ない相談でしょう。時代感覚は年とともに変わって行くのだから、それを強いたら小唄を全滅させるより手が無いわけです。」
「だからその曲と演奏には『垢抜けた』都会趣味がなければいけません。江戸前と粋な代わりに、垢抜けた純和風の都会趣味を強調したいのです。だから私は盛んに新作をするのです。」
「大勢の方に聴いていただくために、ラジオにしてもテレビにしても新しいやり方を考えて小唄の向上を心がける料簡を決めたのです。」
 この"春日とよ"さんの意図したことが、今日のような大きな劇場やホールで演奏する舞台小唄にも発展し、現代の小唄として引き継がれているのですね。 この"春日とよ"さんの意図したことが、今日のような大きな劇場やホールで演奏する舞台小唄にも発展し、現代の小唄として引き継がれているのですね。
春日流は現在、師範が550名を超え、さらにその弟子たちを加えると大変な人数になります。全国に広がる小唄の最大の流派に成長しました。
|