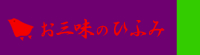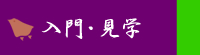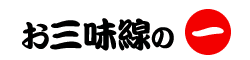|
太棹・中棹・細棹
お三味線には演奏する曲の種類により少しずつ違いがあります。棹の太さの違いで「太棹」「中棹」「細棹」の大きく3つに分類され、さらに糸の太さ、駒やバチの素材や形が使い分けられています。
常磐津、清元、端唄、小唄などは中棹のお三味線をつかいます。太棹の代表は義太夫、細棹は長唄。他にも、棹がとても細く皮をゆるく張った柳川三味線や、胴が大きく棹が太く力強い音のでる津軽三味線など、一口にお三味線といっても色々な種類があり、使う糸の太さや駒、演奏方法などの違いで様々な表情と多様な音色を表現することができるのですね。
|