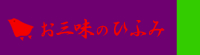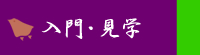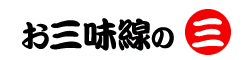|
調弦は調子と本数の組み合わせで複数のパターンがあります。
「調子」は・・・
長調、短調という考え方に似ていますが、曲の雰囲気や響きの違いを出すために曲によって調弦そのものを変えるところが西洋の楽器とは異なるところです。また途中で転調する曲もあり演奏しながら調子を変えることもあります。
代表的な調子は
本調子 :
一の糸に対し、二の糸を完全4度高く、三の糸をオクターブ高く合わせます。
二上り :
一の糸に対し、二の糸を完全5度高く、三の糸をオクターブ高く合わせます。
本調子の二の糸を上げるとこの調子。
三下り :
一の糸に対し、二の糸を完全4度高く、三の糸を短7度高く合わせます。
本調子の三の糸を下げるとこの調子になる。
「本数」は・・・
歌う人の音域にあわせて変える音の高低で「一本」、「二本」と表現します。カラオケでちょっとキーを上げよう、下げようというようなものだと思ってください。男性と女性では同じ曲でも本数を変えますし、その日の唄い手の声のコンディションによって変えることもあります。
「一本」というのは、一の糸の開放弦をオクターブ下のA(ラ)の音に合わせた調子です。半音上げてA♯(ラ♯)にすると二本、さらに半音上げてB(シ)に
すると三本というように、半音ごとに四本、五本となっていきます。
つまり、 四本の本調子というと
一の糸がC(ド)、二の糸はF(ファ)、三の糸は高いC(ド)
四本の二上りは C(ド)−G(ソ)−C(ド)
四本の三下りは C(ド)−F(ファ)−B♭(シ♭)
となるわけです。
|